古本屋まるちゃんの人生卑猥っす!
年末年始は妻の祖母の家にお邪魔し、新年を迎えさせてもらった。
ご馳走をいただき、美味しいお酒も飲めて素敵な一年の始まりだった。
そのとき妻の妹が祖母の家に何冊か本を持ち込んでいたので、ぼくも手にとって彼女の本を少し読ませてもらった。
その中でも時間をかけて読んでしまった面白い本が角幡唯介さんの「探検家の日々本本」である。
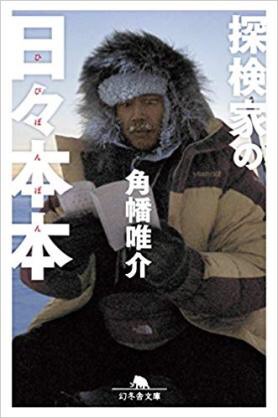
角幡さんは日本の探検家で、光のない「極夜」と呼ばれる現象が起こる海外での探検を描いた「極夜行」で一昨年本屋大賞を受賞している。
この「探検家の日々本本」は、角幡さん独自の目線で面白いと思った本を紹介しながら、本を読むという行為について興味深い言及をしている。彼は作中、読書についてこう語っている。
「このように読書というものは、人の人生を狂わせ、道を踏み外させてしまうかもしれないわけだから、非常に恐ろしい営為だと言える。振り返ってみると、探検家として活動している私も読書には散々振り回されてきた。あのとき、あんな本を読んでしまったせいで、私はあんなところに行くことになってしまったのだ」
僕も本に携わる一人の人間として感じることがある。読書は人間の人生を左右しかねない危険な行為だと常々思っている。
角幡さんのように、多くの冒険家の書いたスリリングな本を読んでしまったために、本人の言う「悪性のロマン」に感染し、山や極地に思いを馳せ、その夢の代償として就職や人並みの生活をあきらめなければならなくなる。
しかし彼の言及はこう続く。
「この際だからはっきり言っておこう。人生をつつがなく平凡に暮らしたいのなら本など読まないほうがいい。しかし、本を読んだほうが人生は格段に面白くなる・・要するに読書には人生の予定調和をぶち壊す毒薬のような破壊力があり、それこそが私が考える読書という営為の最大の美点なのだ」
僕も角幡さんのように読書によって人生の予定調和を狂わされた人間の一人だ。これまで触れてきた本たちの危なっかしくも恍惚な毒牙に触れてしまったおかげで、見事「悪性のロマン」に罹患してしまった。でもいろいろと想像してみると、たしかに彼の言うように本を読んだ方があきらかに豊かな人生を歩めている。
今回は、そのように僕自身が魅了されてしまった本を何冊か紹介したいと思う。
ここで注意したい。自分の人生を狂わせられたくなければ、ここから先の話は読まないことをお勧めする。僕の紹介する本を読んで、仕事を辞めてしまったとか、海外で彷徨うようになってしまったとか文句を言われても、残念ながら責任は取れない。
●野田知佑著「ガリバーが行く」

「〈月曜日〉週末の遊びで疲れているので、家でゆっくり休養する。
〈火曜日〉まだ疲れが残っているといけないので休養予備日とする。
〈水曜日〉と〈木曜日〉休養疲れと飲み過ぎで終日ボー然と過ごす。
〈金曜日〉翌日からの遊びに備えてしっかり休養する。
〈土曜日〉〈日曜日〉マジメに遊ぶ。」
びっくりするような週間予定表で始まる野田知佑さんの「ガリバーが行く」を読んで、僕は「人はこんな自由に生きていいんだ!」と目からウロコが剥がれる鮮烈な思いに駆られた記憶が残っている。
野田さんは日本におけるカヌーイストの第一人者で、日本を始め世界各地の川をカヌーで旅している。作家でエッセイストの椎名誠さんとも親交があり、作中にたびたび椎名さんが登場する。
野田さんの本を読むと、猛烈に旅に出たくなる。しかし野田さんが教える旅とはリゾート旅行ではなく、長期間、誰も住んでいないような辺境の地をひたすら歩んでいく孤独な一人旅だ。会社勤めをしていては野田さんのようなカッコいい旅人にはなれない。一体俺はどうしたらいいんだ・・・
野田さんの作品を読んだ人は野田さんの自由な生き方に惚れ、一人、また一人と文明社会から逸脱してしまうのである。
●ニコス・カザンザキス作「その男 ゾルバ」
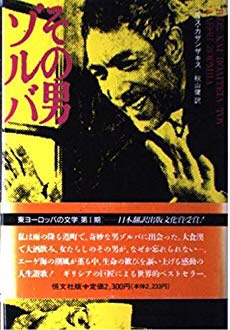
ギリシャの作家、ニコスカザンザキスが遺した小説。
主人公は祖父の遺した鉱山を相続し、その経営のためクレタ島へ向かう。その道中の船で、無骨な労働者ゾルバに出会い、意気投合したゾルバを雇うことになる。
作中、随所に描かれる主人公とゾルバの掛け合いを目にしたら、きっとゾルバという男の生き様にやられてしまうだろう。人生を豪快に、熱く生きるゾルバの姿は、今読んでも読者の琴線に触れるはずだ。
昨年、ひょんなことから日本を旅しているギリシャ人と仲良くなったのだが、彼にニコスカザンザキスの話を聞くと、「もちろん知ってるよ。ゾルバはギリシャじゃ超有名だからね」と生の声を聞かせてくれてたいへん嬉しかった。そう語るソクラテス(そのギリシャ人の名前)もまた、ゾルバに似て長身で豪快な性格だった。社会に対する怒りを原動力に世界を飛び回っているソクラテスからは、どうしてもゾルバの面影を感じてしまった。まるでゾルバが作中から飛び出してきたみたいで、そばにいて何だか不思議な感じだった。
ゾルバやソクラテスを生んだギリシャは、僕が今一番行ってみたい場所だ。
●ロバート・B・パーカー作「初秋」

私立探偵スペンサーを主人公としたハードボイルド小説。スペンサーシリーズとして多くの続編があり、この「初秋」は第7作目。
今回の依頼人は女性。離婚した夫が連れ去った息子のポールを取り戻してほしいという依頼だったが、少年ポールは親の離婚の狭間で材料として扱われ、心を閉ざして何事にも関心を示さない人間になってしまっていた。そんな少年ポールに、スペンサーは彼流のトレーニングでポールの心を開いていく。
スペンサーが人生を何も知らない少年ポールに与える教えは、温かくも本質的なものが多い。その言葉は知らぬ間に、ポールだけでなく現代を生きる僕たち読者に向かって言っているようにも思える。生きるとは何かを問いかけてくる作品だ。
「なんで1400年代のことを書いた本を読むの?」
「当時の人々の生活がどんなものだったか、知りたいのだ。読むことによって、六百年の隔たりを超えた継続感が得られる点が好きなんだ」
「バレエを踊る男は大勢いるよ」
「そうだな」
「彼らはホモだ、と父が言うんだ・・・彼らはどうしてあんなことを言うんだろう」
「なぜなら、その程度の頭しかないからだ。自分たちが何であるのか、あるいはそれを見出す方法を知らない。だから彼らは類型に頼る。・・・君のお父さんは、どうすれば立派な人間になれるのか、知らない、だから、誰かから聞いた単純なルールに従う。自分で考えるより容易だし、安全だ。さもないと、自分で判断しなければならない。」
スペンサーは探偵業の傍ら本をよく読み、体を動かし、自分のことは自分で済ませ、自分の判断で行動する。その姿は一つの自立した大人を見せてくれ、シンプルにカッコいい。そう言った理想像に近づきたくて、僕たちは今日も本を読んでいるのかもしれない。







